Landfall Gamesが開発した2Dアクションシューティングゲーム『ROUNDS』は、そのシンプルな見た目とは裏腹に、プレイヤー間のコミュニケーションや友情に深い影響を及ぼす可能性がある作品だ。果たしてこのゲームは、友情を深めるツールなのか、それとも友人関係を壊す危険な試金石なのか。

この記事では、対戦ゲームを通じて友情や人間関係に対してどのような影響を与えるのかを考察していくニャ。
『ROUNDS』における緊張感

本作は、1対1の対戦型ローグライクアクションゲームである。プレイヤーは両手がだらんとした丸っこいキャラクターを操作しながら、多彩な武器を扱い相手を撃ち抜くことを目指す。先に5ラウンド先取りしたプレイヤーが勝利だ。
本作の最大の特徴は、ラウンドごとに獲得できるアップグレードシステムにある。試合の流れは、まず基本的な銃撃戦から始まる。負けたプレイヤーは強化カードを入手し自身のビルドをアップグレード。強化カードには、弾のバウンス回数を増やす「Bouncy」、射撃速度を向上させる「Fast Bullets」、防御を強化する「Block Cooldown」など、非常に多彩だ。双方のプレイヤーは、互いにビルドを強化し合い、最終的には激しい試合展開となっていくのが常である。
この「敗者が強くなる」というローグライクシステムに、本作の最大の魅力がある。初めは笑いながらプレイしていた友人とのセッションも、試合を続けるうちに「お前はなぜこんなカードを選んだ?」「君はカードに引きが強すぎる。こんなの運ゲーだ」などと、互いの選択に対する指摘が増えていく。このような語らいの中で、その人のゲームに対する価値観が自然と表れ、友人関係に影響を及ぼすこともあるだろう。

相手が連続して『追尾機能』だったり『遠隔操作』など最強カードを引くと、暴言も吐きたくなっちゃうよね。
ゲームが進行するにつれ、勝っているプレイヤーは「次のアップグレードで相手はどれだけ強くなるのか?」と警戒し、負けているプレイヤーは「どんなビルドで逆転するか?」と戦略を練るようになる。劣勢・優勢に関係なく双方のプレイヤーに一定の緊張感が持続するのが、『ROUNDS』の醍醐味だといえよう。
友情に与える影響

ところで、この「敗者が新たな能力を獲得して強化される」というローグライク要素。このシステムの存在が、勝者と敗者の立場を頻繁に入れ替え、初心者と上級者との垣根をなくすバランス的な役割を担う一方で、これによって生じるのは時に友情の破壊であったり、人間関係の破綻である。

その理由について、次の章からさらに掘り下げてみるニャ。
1対1の対戦ゲームにおける、競争と協力のバランス

『ROUNDS』のような対戦型ゲームでは、プレイヤー同士の競争が避けられない。この競争が健全な範囲で行われる場合、友情を深める要素となるが、競争が行き過ぎると「勝つこと」それ自体が目的化し、ゲームプレイの楽しさが損なわれる危険性がある。

うぅ、次こそは勝つ。次こそは勝つ..。
例えば『スマッシュブラザーズ』のようなパーティー要素の強いゲームでは、複数人での同時プレイが可能だ。このため、手加減や戦略を通じてプレイヤーが互いに楽しくプレイすることが求められる。特に、チーム戦やアイテムの使用によるランダム要素が、カジュアルなプレイヤー同士の関係を円滑にし、勝敗よりも娯楽としての要素をより強調している。一方で『ROUNDS』では、1対1の直接対決に特化している。そのため、「真剣勝負」に焦点が置かれるシーンが多い。このような対戦の特性が、プレイヤー間の信頼関係にどのような影響を与えるのだろうか。
ゲームプレイ中の感情と生理的反応

ゲームプレイ中の感情や生理的反応は、友情に影響を与える重要な要素となる。心理学研究によると、勝利時には脳内でドーパミンが分泌され、快感や達成感をもたらし、プレイヤーの自己肯定感を高めるという1。一方、敗北が続くとストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が増加し、怒りやフラストレーションの原因となり、対戦相手への敵意や不満につながる可能性がある。2
特に、競争心が強いプレイヤーにとっては、勝利が自己効力感を強化し、さらなるチャレンジを促す一方、連敗が続くことで自己評価が低下し、ゲームの楽しさを見失うリスクがある。この心理的反応は他の対戦ゲームにおいても同様で、勝敗の繰り返しがプレイヤーの自信や意欲に影響を及ぼすのである。3

確かに負け続けると、現実生活に戻った時にも自己肯定感が低下している気がするよ。
さらに、リアルタイムの対戦ゲームでは、瞬時の判断と反応速度が求められるため、プレッシャーが蓄積しやすい4。これが過度になると、冷静な判断ができなくなり、ミスが増え、相手への苛立ちや焦りが友情のひび割れにつながることもあるだろう。とはいえ、適度な緊張感は集中力を高め、プレイヤー同士の競争を刺激し、ゲーム体験をより充実させる要素となる側面があるため、一概に否定的になれないのが難しいところだ。
このように、『ROUNDS』のような1対1対戦ゲームは、感情と生理的反応が密接に結びついており、これを理解しコントロールすることが、友情や人間関係を維持するための重要な鍵となると言えるわけである。
これはあらゆる対戦ゲームにも共通しており、勝敗の繰り返しがプレイヤーの自己評価に大きく影響を及ぼす。特に、リアルタイム対戦ゲームでは、瞬時の判断と反射が求められ、相手への苛立ちや焦りが友情の亀裂を生む場合もあるので注意が必要といえよう。
友情を保つための工夫
『ROUNDS』をプレイする際、友情を維持しつつ楽しむためのいくつかの工夫が有効である。

対戦ゲームにおける友情維持に関する研究によると、プレイヤー間の明確なコミュニケーションと、共通の目標設定が重要であると指摘されてるみたい。(参考記事:Johnson, D., & Wiles, J., 2019, 『Video Game Social Dynamics』)。そこで、いくつかの解決策を考えてみたよ!
- 事前にルールやプレイスタイルを共有する – 「カジュアル」か「真剣勝負」かを明確にしておくことで、双方の期待値を調整できるだろう。研究によれば、プレイスタイルの一致がゲームの楽しさを増し、ストレスを軽減する効果があるという5。
- 試合後の振り返りを行う – フィードバックを通じて互いのプレイスタイルを尊重し、学び合う機会を設けるのも有効だ。特に、建設的なフィードバックは、対戦相手への理解を深め、友情を強化する手段として機能するという6。
- ストレスを適切にコントロールする – 勝敗にこだわりすぎず、ゲーム外でのコミュニケーションを大切にするのもポイント。研究では、適切なストレス管理が、競争のプレッシャーを軽減し、長期的な関係の維持につながることが示されており興味深い7。

以上の要素を留意できれば、『ROUNDS』をより楽しみながら、友情を長続きさせることができると思うニャ。
結論

『ROUNDS』は、単なる対戦ゲーム以上の要素を持つ作品だ。勝敗の繰り返しによってプレイヤー同士の絆が試され、友情が深まることもあれば、関係に亀裂が入ることもあるだろう。競争が友情に与える影響は、プレイヤーの姿勢や関係の在り方に大きく依存する。特に、本作のユニークなアップグレードシステムは、勝者と敗者の立場を逆転させることで、単純な実力勝負とは異なる複雑な心理的影響をもたらす存在だといえよう。
重要なのは、ゲームを「楽しむ」ことを前提とし、勝敗にこだわりすぎず、互いの成長や学びの場とすることである。プレイヤーが競争を受け入れつつ、相手へのリスペクトを保つことが、友情の維持につながるのではないか。本作を通じて、プレイヤーは自らの感情をコントロールし、健全なコミュニケーションを通じて互いを理解する機会を得ることを目指すわけだ。
また、『ROUNDS』のような1対1対戦ゲームは、リアルな人間関係と同様に、競争と協力のバランスを試される場でもある。であれば、ゲームが終わった後のフィードバックや、共通のルール作りが、友情を円滑にする要素として重要だろう。最終的に、『ROUNDS』はプレイヤーの価値観や競争意識を映し出す鏡とも言えるのではないか。

競争を健全に楽しみ、互いのプレイスタイルを尊重することが、友情を長続きさせる鍵となるんだニャ。

所詮ゲーム、されどゲームなのだ。ゲームに対する向き合い方は多様であっていいけど、感情に左右されすぎないよう気を付けよう!
参考文献
- Koepp, M. J., Gunn, R. N., Lawrence, A. D., & Grasby, P. M., 1998, 『Evidence for striatal dopamine release during a video game』, ↩︎
- Smith, J. & Brown, A., 2021, 『ゲームの心理学』 ↩︎
- Deci, E. L., & Ryan, R. M., 2000, 『Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being』 ↩︎
- Yerkes, R. M., & Dodson, J. D., 1908, 『The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation』 ↩︎
- Hostility is associated with self-reported cognitive and social benefits
across Massively Multiplayer Online Role-Playing Game player-roles
Smith, Ciaran M.; Rauwolf, Paul; Intriligator, James; Rogers, Robert D. ↩︎ - Kaye, L. K., & Bryce, J., 2014, 『Gaming and Interpersonal Relationships』 ↩︎
- Hancock, P. A., & Szalma, J. L., 2008, 『Performance under stress』 ↩︎
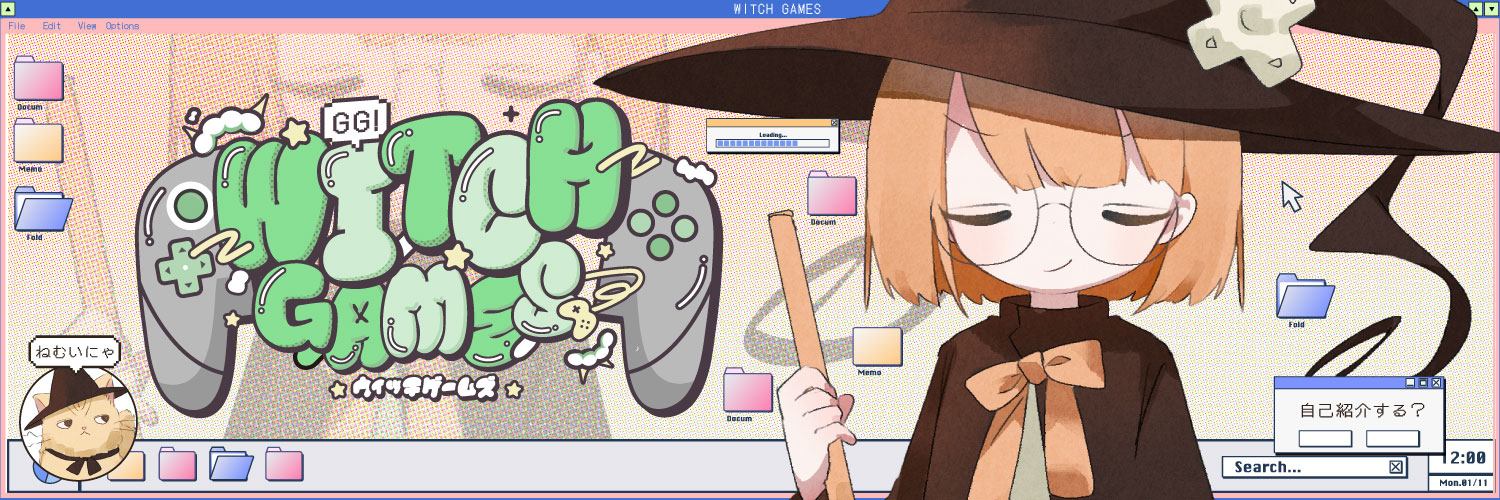



コメント